要約
明治政府が派遣した岩倉使節団は、近代化を目指す日本の未来を背負って世界一周の旅に出ました。アメリカやヨーロッパ諸国を訪れた使節団は、各国の政治制度や産業、教育などを学び、明治日本の礎を築く知見を得ました。本記事では、岩倉使節団の目的、訪問先、影響、そして彼らが目にした“近代化の衝撃”を、会話形式でわかりやすく紹介します。
ミホとケンの対話

ケン、“岩倉使節団”って知ってる?

うーん…岩倉?お菓子の名前?

違う違う(笑)。明治時代に日本が世界を見に行った外交団のことだよ

へぇ〜!外交団って何しに行ったの?

一番の目的は“条約改正”と“近代化のお勉強”だったの

条約って、国同士の約束のこと?

そう!日本は江戸時代の終わりに不平等条約を結んじゃってたから、それをなんとかしたかったのよ

なるほど!でも、いきなり世界に行っちゃうってすごいね

そうなの。しかも1871年に出発して、アメリカから始まってヨーロッパ諸国をぐるっと回ったの

えっ、明治の人たちが世界一周!? 飛行機ないよね?

もちろん船と汽車!1年10か月もかけて回ったのよ

うわー!修学旅行どころじゃない…

しかも使節団のメンバーがまたすごいのよ。岩倉具視、大久保利通、木戸孝允、伊藤博文もいたの

日本の歴史の教科書で見た名前ばっかり!

でしょ?それに彼らは各国の制度を細かく調査して、帰国後の改革に活かしたの

どんなことを学んだの?

例えばアメリカでは教育制度、イギリスでは議会制度、ドイツでは軍事や行政組織なんかを見てきたわ

ってことは、日本の学校とか政治って、その影響を受けてるってこと?

そうなの。帰国後の明治政府の改革には、使節団の経験が反映されてるの

すごい…世界を見て帰ってきて、日本をアップデートしたんだね!

うん!でも残念ながら、条約改正はその場ではうまくいかなかったの

えっ、じゃあ失敗?

いえいえ。現地で改正の困難さを理解したことが、後の外交戦略に繋がったのよ

なるほど〜。結果的には大きな意味があったんだね!

その通り!岩倉使節団の旅は、近代国家としての日本の第一歩だったの
さらに詳しく

1872年、明治4年12月、サンフランシスコ到着直後の岩倉使節団の面々。左から木戸孝允、山口尚芳、岩倉具視、伊藤博文、大久保利通。
岩倉使節団とは?
岩倉使節団(いわくらしせつだん)は、明治政府が近代国家建設を目指して1871年(明治4年)に派遣した大型の外交・視察団です。正式名称は「特命全権大使米欧回覧使節団」といい、日本政府の要人を中心に総勢100名を超える大規模な構成でした。
中心人物は岩倉具視(いわくらともみ)で、大久保利通、木戸孝允、伊藤博文、山口尚芳らが副使として同行しました。また、若手官僚や通訳、留学生も多数参加しており、単なる外交団というよりも「国家的な学びの遠征」とも言えるものでした。
使節団の目的とその背景
第一の目的は、幕末に欧米列強と結ばされた「不平等条約」の改正です。日本は安政の五カ国条約などにより、関税自主権がなく、外国人には治外法権が認められるなど、国家主権を著しく制限されていました。これを是正し、対等な国際関係を築くため、欧米諸国と交渉を行う必要がありました。
第二の目的は、欧米の政治、軍事、教育、産業、文化などを視察し、日本の近代化に役立てることです。明治維新直後の日本は、国内の政治体制や産業基盤がまだ整っておらず、「文明開化」の方針のもと、欧米の制度を参考にして国づくりを進めていこうとしていました。
世界一周の行程と見聞
使節団は1871年12月、横浜港を出発。まずアメリカに向かい、ワシントンD.C.ではグラント大統領と面会し、条約改正の予備交渉を行いました。結果として条約改正そのものは「まだ日本の制度が未熟である」として受け入れられず、交渉は失敗に終わります。
その後、使節団はイギリス、フランス、ベルギー、オランダ、ドイツ、ロシア、イタリア、スイス、オーストリア、スウェーデンなど、ヨーロッパ諸国を歴訪。立憲君主制、議会制度、教育機関、軍事制度、交通インフラ、工業技術などを視察し、膨大な知識を持ち帰りました。
約1年10か月、約30か国を訪れた彼らの旅は、世界一周の形となり、1873年9月に帰国します。
得られた成果と明治国家への影響
条約改正こそ失敗に終わったものの、この旅で得られた知見は、日本の制度整備に極めて大きな影響を与えました。
たとえば、アメリカで学んだ「普通教育の普及」は、1872年の学制発布に反映され、日本に初めての全国的な教育制度が導入される契機となりました。
ドイツで見た中央集権的な官僚制度は、のちの内務省の構築や徴兵制に影響を与えています。イギリスでの議会制度視察も、日本が後に立憲君主制と憲法制定(大日本帝国憲法)を導入するうえで参考となりました。
また、殖産興業政策のもと、製糸業や鉄道などの産業基盤整備にも視察成果が活かされ、日本は急速に近代化の道を進みます。
留学生たちの役割
使節団に随行した10歳前後の子どもたちは、長期間現地に残されて教育を受けました。彼らはのちに帰国し、近代日本の各分野で重要な役割を果たします。特に有名なのが津田梅子です。彼女はアメリカで女性教育を学び、帰国後に女子英学塾(のちの津田塾大学)を創設し、女性の社会進出に大きく貢献しました。
また、当時の使節団が記録した『特命全権大使米欧回覧実記』は、視察の詳細な記録として現代でも貴重な史料となっています。
内政への波紋と帰国後の展開
使節団が世界を回っている間、日本では西郷隆盛や板垣退助らが留守政府を運営していました。しかし使節団が帰国した直後、政府内部では「征韓論」をめぐる対立が激化。岩倉具視や大久保利通らは対外強硬派を抑え、内政重視の姿勢を貫いたため、西郷らが下野する「明治六年の政変」が発生します。
このように、使節団の旅は外交・近代化だけでなく、国内政治の方向性にも大きな影響を与えたのです。
まとめ
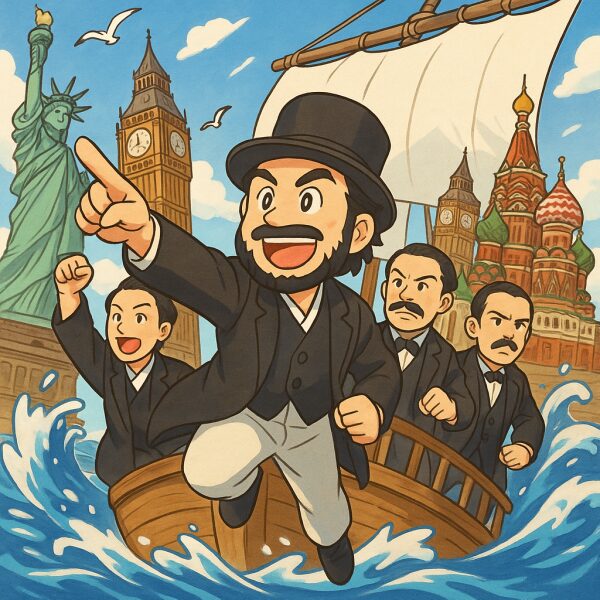
岩倉使節団は、明治初期の日本が世界に目を向け、近代国家への道を模索した象徴的な外交・視察プロジェクトでした。条約改正こそ実現しなかったものの、その経験は教育・政治・産業など多岐にわたる分野に影響を与え、明治維新後の日本の方向性を決定づけました。


コメント