要約
平安時代の貴族・藤原道長は、摂政として絶大な権力を握り「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の…」という有名な和歌を詠みました。この歌は、満月のように欠けるところのない自分の権力を表現したもので、まさに頂点を極めた男のドヤ歌ともいえます。この記事では、その背景や意味、藤原道長の人生を会話形式でわかりやすく解説します。
ミホとケンの対話

ケン、“この世をば わが世とぞ思ふ”っていう歌、聞いたことある?

うーん、なんかちょっと中二病っぽい響きだね…誰が詠んだの?

ふふ、平安時代の超大物、藤原道長だよ。まさにリアル最強の貴族って感じ!

え!その人、なんでそんな自信満々な歌を詠んだの?

この歌、実は道長が摂政になって、娘たちを天皇の妃にして、自分の力が絶頂のときに詠んだものなの

え、えー!つまり、『この国はもうオレのもんだ!』って宣言した感じ?

そうそう、“満月のように欠けるところがない”っていう意味も込めて、“望月の欠けたることもなしと思へば”って続くんだよ

めちゃくちゃドヤってるじゃん!でも、そのくらいのこと言えるってすごいな

道長は、摂関政治を極めた人。娘を3人も中宮にして、自分の孫が次々天皇になったの

もはや将軍よりすごいんじゃ…

当時は天皇よりも実権を握ってたと言われてるよ。裏ボス的存在かな

じゃあ、その和歌って、いつ詠んだの?

1018年、娘・威子(いし)が中宮になったとき、宴の中で詠んだの

宴でそんな歌を詠むって、平安貴族、派手すぎない?

でもそれが文化だったの。自分の気持ちを和歌で表現するのがステータスだったのよ

…てことは、今で言うSNSの“俺すごいだろ”投稿みたいな?

まさに!でも和歌でさりげなく、優雅にドヤるのが平安流

和歌って奥深い…でも道長の人生、成功しかなかったの?

表面上はね。でも晩年は病に苦しんで、仏教に傾倒していったの

あ、なんか…そう聞くと少し人間っぽいな

そうなのよ。『この世をば~』の歌も、永遠じゃなかったってところがまた味があるよね

うん、満月もいつかは欠けるんだもんね…なんかロマンあるなあ

詠まれた背景を知ると、ただのドヤ歌じゃなくて、時代の鏡にも見えてくるでしょ?
さらに詳しく

「紫式部日記絵巻」より
藤原道長とは
藤原道長(ふじわらのみちなが、966年〜1028年)は、平安時代中期を代表する貴族で、政治家としても極めて優秀でした。彼は藤原北家の出身で、父・藤原兼家の後を継ぎ、兄たちの死後に一門の実権を握ります。
摂関政治の絶頂期を築いた男
道長が活躍した時代には、天皇が若年で即位することが多く、摂政や関白といった役職を通して、実質的な政権運営が行われていました。これを「摂関政治」といいます。
娘たちを天皇家に嫁がせる戦略
道長は政治力と婚姻政策を駆使し、三人の娘(彰子・妍子・威子)を天皇に嫁がせ、天皇の外戚として絶対的な権力を得ました。その結果、孫が天皇になるという状況まで作り上げたのです。
「この世をば」の歌に込められた意味
有名な歌「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば」は、道長が摂政に任命された1018年、娘・威子の中宮(皇后)昇格を祝う宴の席で詠まれました。
この歌には、「この世界はまるで自分のもののようだ。まるで満月のように、欠けるところが何もない」という意味が込められています。道長は、この和歌を通して、自らの政治的完成と家の栄華を満月にたとえました。
和歌に隠された「栄華と無常」
当時の貴族たちは、和歌を単なる自慢ではなく、感情や哲学を含ませる手段として用いていました。満月は「完全」を象徴すると同時に、「やがて欠けていく運命」も暗示します。
このことから、「この世をば」はただのドヤ歌ではなく、一時の栄光の儚さまでもがにじむ一首とも解釈されています。
晩年の道長と仏教への傾倒
道長は晩年に重病を患いました。特に甘味好きがたたり、糖尿病のような症状に苦しんだとされます。その苦しみの中で、彼は次第に仏教に救いを求めるようになります。
法成寺の建立
彼は都に大寺院「法成寺」を建立し、写経・仏像造立・寄進などを積極的に行いました。これは、当時の貴族が極楽往生を願って行う信仰活動の一環でした。政治の頂点にいた人物が、やがて死と向き合い、精神的な救いを求めていたというのは非常に興味深い点です。
現代に残る道長の評価
「この世をば」の和歌は、現代でも自己肯定の象徴や栄光の絶頂の表現としてたびたび引用されます。一方で、その後に続く人生からは、「栄華はいつまでも続かない」というメッセージも感じ取ることができます。
藤原道長の生涯は、権力の追求とその代償、そして人間としての内面の変化を通じて、平安時代の精神文化や価値観を色濃く映し出しているのです。
まとめ
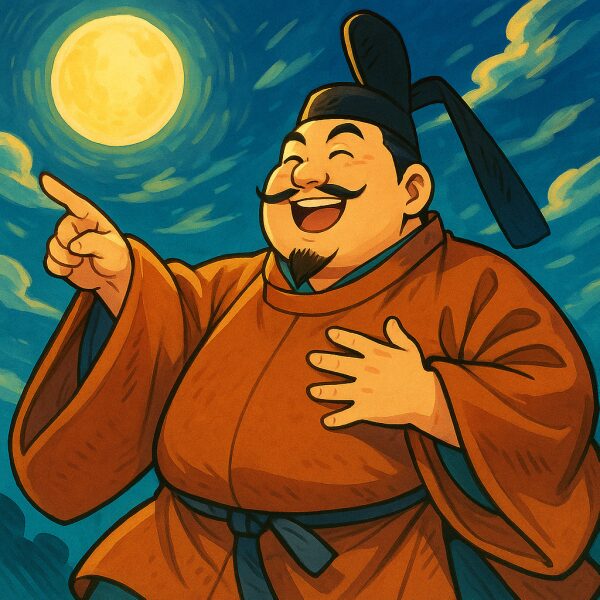
藤原道長の「この世をば」の和歌は、彼が政治的な頂点に立った瞬間に詠まれた、時代を象徴する一首です。満月にたとえた権力の完成は、平安貴族の美意識と自負心をよく表しています。その一方で、晩年の道長は病に悩み、仏教に救いを求めたことから、栄華と無常というテーマも読み取れる和歌です。


コメント