要約
渋沢栄一といえば、日本資本主義の父として知られる偉人ですが、実は子供が20人以上いたことをご存じでしょうか?本記事では、彼の家庭事情や子供たちの人生、当時の家族観にまで迫ります。現代では考えにくい「大家族」を支えた渋沢の背景や、その影響力を解説します。
ミホとケンの対話

ねぇケン、渋沢栄一って知ってる?

あ!お札の人でしょ?なんか新しい一万円札の!

そうそう!でもね、彼のすごさはお金だけじゃないのよ

へー、何がすごいの?

なんと、子供が20人以上いたの!

えっっ!? サッカーチーム2つ分!?

そのくらいの勢いよ(笑)しかも、正妻と妾との間にたくさんいたの

え、妾って何?お妾さん?

うん、当時は妾を持つのは珍しくなかったの。特に地位がある男性はね

じゃあ、みんな一緒に住んでたの?

住まいは分けてたみたいだけど、栄一は家族全体を支えていたわ

すごいなー…仕事して、子育てもして?

正確には、育てるのは妻や妾たちが中心だけど、教育にはすごく力を入れていたの

教育って、どんなふうに?

例えば、子供たちには厳しくも愛情を持って接して、才能を伸ばすようにしてたの

ちゃんと子供のこと見てたんだ…

うん。あとね、養子に出したり、縁組したりもしてた

え、子供を養子に!?

当時は家を守ることが大事だったから、実子でも他家に出して跡継ぎにするのも普通だったのよ

現代と感覚が全然違うんだね

そう。でもそれが、栄一の“家”だけじゃなく、“国”の礎にもなっていったの

えっ、子供たちが日本のために何かしたの?

そう、子供や孫たちも政治家や実業家になって活躍してるの

うわー…まさに“ファミリービジネス”!

いいこと言うね!渋沢家はまさに、国家レベルのファミリービジネスだったかも

すごすぎるよ渋沢さん…もう、現代のスーパーお父さんだよ…!

まさにね。でも、家庭と国の両立って、すごいバランス感覚だったと思うわ
さらに詳しく

渋沢栄一(渋沢史料館所蔵)
渋沢栄一とは?
渋沢栄一(1840〜1931)は、埼玉県深谷市出身の実業家であり、日本の近代経済の礎を築いた人物です。幕末には尊王攘夷運動に傾倒し、やがて徳川慶喜に仕えることで幕臣となりました。
その後、パリ万博視察のために渡欧し、西洋の近代的な経済制度に触れたことが彼の人生を大きく変える転機となります。明治政府に仕えたのち、民間での活動に転じ、第一国立銀行(現・みずほ銀行)をはじめとする約500以上の企業や団体の設立に関わり、「日本資本主義の父」と称される存在になりました。
なぜ子供が20人以上いたのか?
渋沢栄一には、正妻・千代との間に4人の子どもがいましたが、千代の死後に妾を持ち、複数の女性との間にさらに多くの子をもうけました。最終的に確認されているだけでも20人以上の子どもがいたとされています。
当時、妾を持つことは社会的地位のある男性にとっては決して珍しいことではなく、むしろ家の存続や人脈の拡大といった観点から積極的に受け入れられていました。渋沢もその時代の価値観に従っていたといえるでしょう。
また、「家」という概念が非常に重要視されていた明治期において、子供が多いことは家の繁栄を示すステータスともなりました。特に、当主としての責任を果たすためには、跡継ぎを確保する必要があり、万一に備えて複数の男子を育てておくのが一般的でもありました。
子どもたちの進路と活躍
渋沢の子どもたちは、その名声と教育方針のもとで大いに活躍しました。長男・渋沢篤二は実業界に身を置き、後に父の事業を支える存在となりました。また、孫にあたる渋沢敬三は、日本銀行総裁、大蔵大臣などを歴任し、日本経済の中核を担う人物として知られています。
そのほかの子や孫たちも、それぞれの分野で教育を受け、官界・財界・学界・軍界など多様な方面で頭角を現しました。まさに「渋沢ファミリー」は、一種のエリート人材育成機関のような役割を果たしていたともいえるでしょう。
明治時代の家族制度と妾制度
明治期の日本では、まだ封建制度の名残が色濃く残っており、「家制度」が非常に重視されていました。家は個人よりも優先される単位であり、家の名を守り、血筋を絶やさないことが重要視されました。
このため、正妻に子がいない場合や男子に恵まれない場合には妾を持つことも許容され、むしろ家の責任として奨励される場合もあったのです。
渋沢栄一もその価値観に基づき、家族を増やし、家の影響力を強化していきました。妾との子どもであっても、教育には差をつけず、きちんと育てていたという点において、渋沢の公平さと先進的な教育観が見て取れます。
教育と“家庭内国家”という思想
渋沢は教育に非常に熱心で、「学問こそ国を支える根幹である」という信念を持っていました。自らの子どもたちにも、ただ家を継がせるだけでなく、人格形成や社会的責任を意識させるような教育を施しました。
礼儀作法、勤労、倫理観といった面も重視され、まるで国家運営を家庭内でも実践しているかのような統治を行っていたといえます。
また、子どもたちの将来については自らの人脈を活かし、縁組や進学先なども積極的に支援しました。このような支援の結果、渋沢家は一族全体が影響力を持つ“人材ネットワーク”として社会に広がっていくのです。
「家」から「国」へとつながる視点
渋沢の家庭観は、単なるプライベートな家族愛ではなく、「家を整えることは国を整えること」という思想に根ざしています。家の中に秩序と教育を行き渡らせることが、そのまま社会の安定に繋がると考えていたのです。
このような価値観は、彼が唱えた「道徳経済合一説」とも密接に関係しており、経済活動を行う上での倫理観や人間的成長を重視する姿勢が、家庭運営にも反映されていました。
まとめ
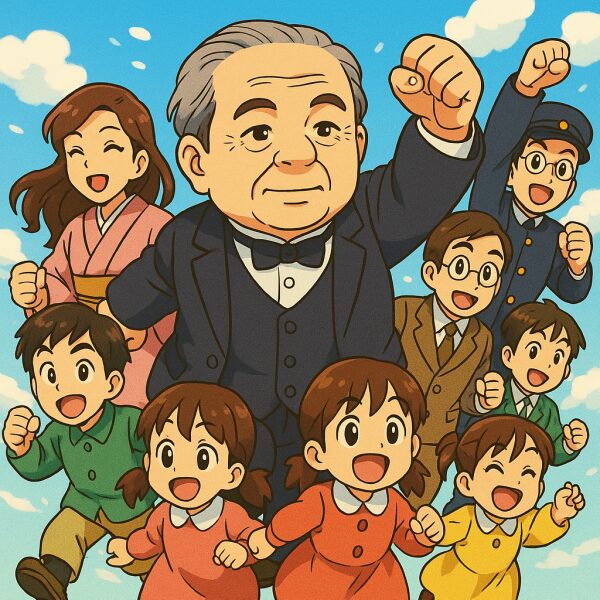
渋沢栄一は、日本の経済をつくり上げた偉大な実業家であると同時に、20人以上の子供を抱える大所帯の家長でもありました。家族を一つの社会と捉え、教育や縁組に力を注いだ彼の姿からは、当時の家制度の在り方と、国家を見据えた長期的な視点が垣間見えます。


コメント