要約
中国戦国時代の名将・白起が率いた秦軍は、長平の戦いで趙軍を破り、降伏した約40万人の兵士を生き埋めにしたと伝えられています。この行為は戦術か、あるいは非道か。背景には秦の統一政策や白起の個人的信念も関係していたようです。この記事では、この衝撃的な事件の真相と、白起という人物の本質に迫ります。
ミホとケンの対話

ケン、“白起”って聞いたことある?

うーん…全然知らないかも。何した人なの?

中国の戦国時代に活躍した、秦の超すごい将軍なの

へー、戦国時代って日本の戦国時代?

いや、これは中国の方。日本より何百年も前の話ね

すごい昔だ…その人、どんな戦いをしたの?

“長平の戦い”っていう、戦国時代最大級の戦いで活躍したのよ

どんな戦いだったの?

秦と趙って国が戦ってて、白起は秦軍の総大将として趙軍を圧倒したの

へえ?強かったんだね!どれくらい勝ったの?

趙軍の兵士を一気に捕虜にして、その数なんと約40万人

え!?40万人って!それ、どうやって面倒みたの?

実はね…白起はその40万人、処刑しちゃったの

……え、え!? 全員!? なんでそんなことを…!

補給が足りなかったのと、また敵になる可能性を恐れたのが理由らしいの

えぇ…降伏した人たちなのに…ひどくない?

当時は、勝つためには手段を選ばないことが正義とされてた面もあるの

うーん…すごいけど、ちょっと怖いなあ

白起自身は戦術家としては天才で、“百戦百勝”って言われるくらいなのよ

じゃあ王様からも信頼されてたんじゃない?

実はそこが皮肉でね…あまりに強すぎて、王様に警戒されるようになったの

えっ、強いから疑われるの?信じてくれないの?

うん。白起は次の戦にも出るよう命じられたけど、拒否したの。そしたら…

そしたら?

捕らえられて、最後は自害するよう命じられたの

えええっ…!自分の国に殺されるって…それはあんまりだよ

白起の生涯って、まさに“強すぎた英雄の悲劇”って感じだよね

なんかすごい話だった…。ただの武将じゃないんだね

うん。冷徹な判断も、時代と運命に翻弄された面もあるよね。
さらに詳しく
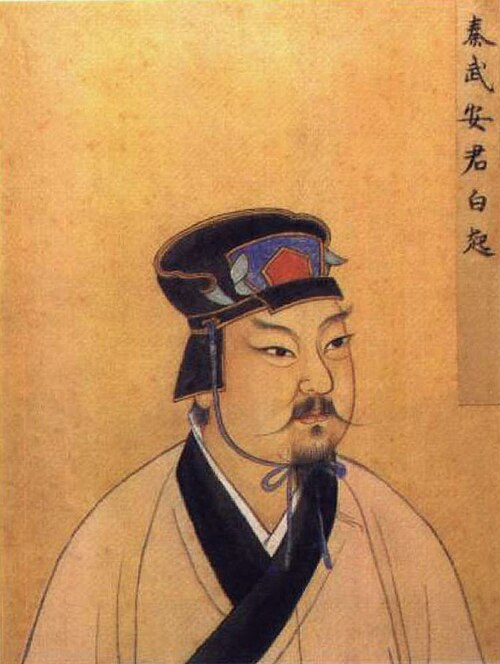
白起
白起とは
白起(はくき)は、中国戦国時代における秦の名将であり、戦術の天才と称される人物です。生年は定かではありませんが、紀元前257年に自害するまで、数々の戦場で功績を挙げました。彼は戦いのたびに勝利を重ね、「百戦百勝」とまで評された将軍です。
白起の軍事的特徴は、単なる力押しではなく、兵糧攻め・心理戦・計略といった多角的な戦法を巧みに操った点にあります。また、無駄な戦闘を避け、相手のミスを突いて一気に勝機を掴む手腕にも長けていました。
長平の戦いとは
戦いの背景
紀元前260年、秦と趙という二大国が、現在の山西省にあたる長平で激突しました。この戦争は、戦国時代でも屈指の大規模戦であり、約4年間の膠着状態が続いた末、秦が白起を総司令官に任命することで流れが大きく変わります。
白起はすぐに敵の補給線を断ち、長期戦を強いられた趙軍は兵糧不足に悩まされました。さらに、趙の名将・廉頗(れんぱ)に代えて若い将軍・趙括(ちょうかつ)が指揮を執るようになると、白起はこれをチャンスととらえて大攻勢を仕掛けました。
白起の戦術
白起は敵の士気を下げるため、偽の投降兵を送り込んで内部撹乱を行い、最後には全軍包囲作戦を成功させました。趙軍は逃げ場を失い、40万人以上の兵が捕虜となったといわれています。
捕虜40万人の生き埋め処刑
戦いの後、白起はこの膨大な数の降伏兵をどう扱うかという決断を迫られました。結果、彼は約40万人を生き埋めにして処刑したのです。
なぜここまで過激な選択をしたのか?
その理由は大きく3つあると考えられています。
- 食糧不足:秦軍も長期戦で疲弊しており、膨大な捕虜を養う余裕がなかった。
- 軍事的リスク:捕虜が再び武装して反乱を起こす可能性を排除したかった。
- 見せしめ効果:他国に対する徹底的な威圧と、心理的支配を狙った。
この決断は、現代の倫理観から見ればあまりに過酷ですが、当時の戦国時代においては「戦略的な判断」として一部では理解されていました。しかし、その残酷さは後世の人々に大きな衝撃を与え、白起の評価には常に賛否がつきまといます。
白起の最期と秦の内情
戦いに勝ち続けた白起でしたが、その成功がやがて秦国内の不和を生みます。彼の権威は軍内部のみならず、政治にも大きな影響を与えるようになり、秦王・昭王や重臣たちは、次第に白起を恐れるようになります。
出兵拒否と疑念
白起は再度の出兵命令を拒否しました。理由は、兵の疲弊や戦略的な不利を感じ取っていたためです。しかし、これが「王命に逆らった」と見なされ、白起は罪人として扱われます。
自害の命令
最終的に、白起には自害が命じられました。彼はその命に従い、紀元前257年に命を絶ちました。この出来事は、「英雄が国家の恐れによって葬られる」という、歴史における悲劇の一つとして語り継がれています。
白起の評価と歴史的意義
白起は間違いなく戦国時代を代表する将軍の一人であり、その戦術の鋭さや判断力は、後の兵法書でもしばしば取り上げられています。一方で、その冷酷さと大量処刑の事実は、倫理的な評価を難しくしており、まさに「評価が二分される英雄」です。
その死後、秦は統一戦争を加速させ、ついに始皇帝の時代に中国を統一します。白起の功績がなければ、その統一は数十年遅れたかもしれないとも言われています。
まとめ
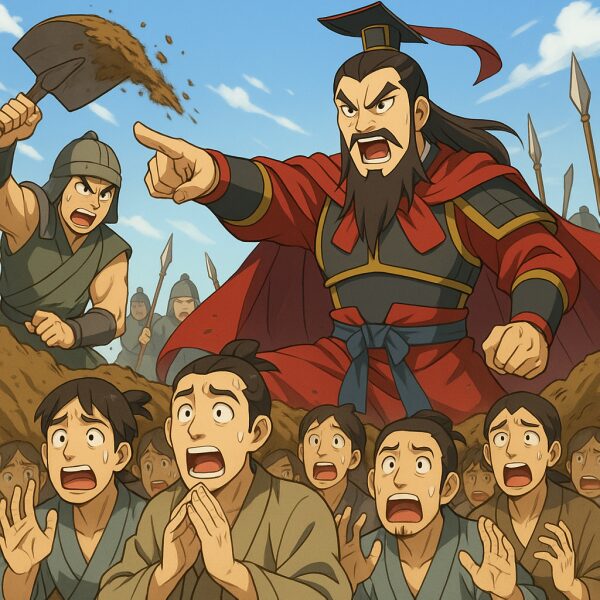
白起は秦の名将として戦国時代に名を馳せ、特に長平の戦いでは驚異的な戦術で趙軍を圧倒しました。その戦いの結果、約40万人の降伏兵を生き埋めにするという壮絶な決断を下します。この行為は後世に大きな議論を残しましたが、彼の決断と死は、戦国の非情さと権力闘争の厳しさを象徴しています。


コメント