 近現代
近現代 アインシュタインの「舌ペロ」ポーズが歴史的名写真になったワケ
要約1951年、アルベルト・アインシュタインが舌を出した写真は、今や世界的に有名なユーモラスな一枚です。この写真には、アインシュタインの性格や時代背景、撮影当時の状況が反映されています。実はこの舌出しにはちょっとした偶然と彼の茶目っ気が関係...
 近現代
近現代  戦国時代
戦国時代  古墳・飛鳥時代
古墳・飛鳥時代  鎌倉時代
鎌倉時代 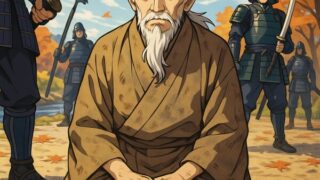 戦国時代
戦国時代  中世
中世  平安時代
平安時代  江戸時代
江戸時代  戦国時代
戦国時代  江戸時代
江戸時代